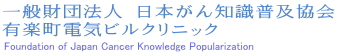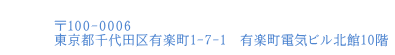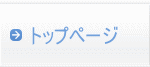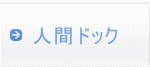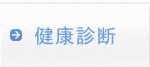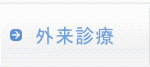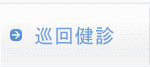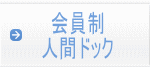健康かわら版 4月号 「痛風・高尿酸血症」について
新緑の映える、美しい季節になりました。お花見や歓送迎会などでお酒を飲む機会も多い時期です。今月は痛風・高尿酸血症についてお話します。痛風発作は発汗で水分不足になると起こりやすくなります。これから気温が高くなると脱水状態になり易く、特に夏は要注意です。健診結果で尿酸値が高い方は、今から食事などに注意し、辛い発作が起きるのを防ぎましょう。
尿酸とは
尿酸とは新陳代謝の結果生じる老廃物のひとつで、本来一定量以上は尿や汗などに含まれて排出されるものです。しかし様々な要因で体内で増えすぎると、血液中の尿酸値が高まり、「高尿酸血症」という状態になります。
参考:基準値 7mg/dL未満
尿酸の生成排泄のバランスが保たれていると、血液の尿酸値もほぼ一定に保たれます。バランスが崩れる場合としては以下の型があります。
生成過剰型 : 尿酸の生成量が多くなり、排泄が追いつかなくなる場合
排泄低下型 : 尿酸の排泄機能が低下し、排泄量が減る場合
混合型 : 生成過剰と排泄低下が同時に起こっている場合
| 高尿酸状態が続くと、血液中に溶けきれなくなった尿酸が結晶になります。結晶化すると溶けにくくなり、身体の様々な部位に沈着します。代表的なのが痛風発作です。 |  尿酸の結晶 |
痛風発作とは
尿酸の結晶が関節内に出来ることで、激しい痛みが生じます。発作を起こした関節は赤くはれ上がり、「風が吹いても痛い」状態になることから痛風と言われています。発作を起こしやすいのは、足の親指の付け根の部分ですが、足首や膝に発作が起きることもあります。
・慢性腎臓病 : 腎臓の尿細管に尿酸の結晶が沈着し、腎臓の機能が低下します。
・尿路結石 : 腎臓や尿管などに尿酸の結晶が固まり、結石を作ります。
・動脈硬化 : 尿酸が刺激要因となり、血管の炎症が生じます。動脈硬化が進むと、心臓や脳を含む全身の血管に影響が出ます。
尿酸値を下げるために、生活習慣を改善しましょう
・食べ過ぎない。食事量を減らして、摂取カロリーを抑えましょう。
・脂質や塩分を控える。
・プリン体を多く含む食品を控える。
・アルコールを摂り過ぎない。
・水分を多めに摂り、尿量を増やす。
・野菜や海藻類を十分摂り、尿をアルカリ性に保つ。
・適度な有酸素運動をする。
※生活習慣を改善しても尿酸値が下がらない場合や、痛風発作を起こした場合は薬物治療が必要になります。尿酸の生成を抑える薬や、排泄を促進する薬などを使い、血中の尿酸値を標準範囲内に抑えます。
プリン体摂取量の目安
普段の食事でも食材に注意し、尿酸の元となるプリン体を取りすぎないようにしましょう。摂取の目安量として1日400mgを超えないようにしましょう。(「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」より)
■プリン体の多い食品
| とても多い (300mg/100g以上) |
煮干、カツオ節、干し椎茸、アンコウの肝、鶏レバー、真イワシ(干物) |
|---|---|
| 多い (200〜300/100g) |
豚レバー、大正えび、真アジ(干物)、牛レバー、カツオ(生)、オキアミ、真イワシ(生) |
| やや多い (200mg/100g以下) |
内臓肉(豚腎臓、牛心臓など)、ニジマス、クルマえび、スルメイカ、真アジ(干物)、乾燥大豆 |
アルコール摂取量の目安
ビールには麦芽由来のプリン体が含まれています。また、アルコール自体に尿酸の排泄を妨げる作用があります。お酒の種類に関係なく、適量範囲内の飲酒を心掛けましょう。
適量は1日1単位以内とされています。お酒の「1単位」とは、純アルコールに換算して20gです。純アルコールは以下の式で計算できます。
1単位のお酒の量(種類別)
| お酒の種類と量 | アルコールのカロリー |
| ビール中ビン1本(500ml) | 200kcal |
| 日本酒1合(180ml) | 172kcal |
| ワイン・ブラス2杯(240ml) | 146kcal |
| 焼酎0.6合(110ml) | 146kcal |
| ウィスキー ダブル1(60ml) | 142kcal |
過剰なストレスも尿酸値を上げるといわれています。また激しい運動でも尿酸値は上がってしまいます。ストレスは、食事やアルコール・激しいスポーツではなく、軽い運動やリラックスすることで解するようにしましょう。食事内容や生活を見直し、ご自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。
過去の健康かわら版はこちら